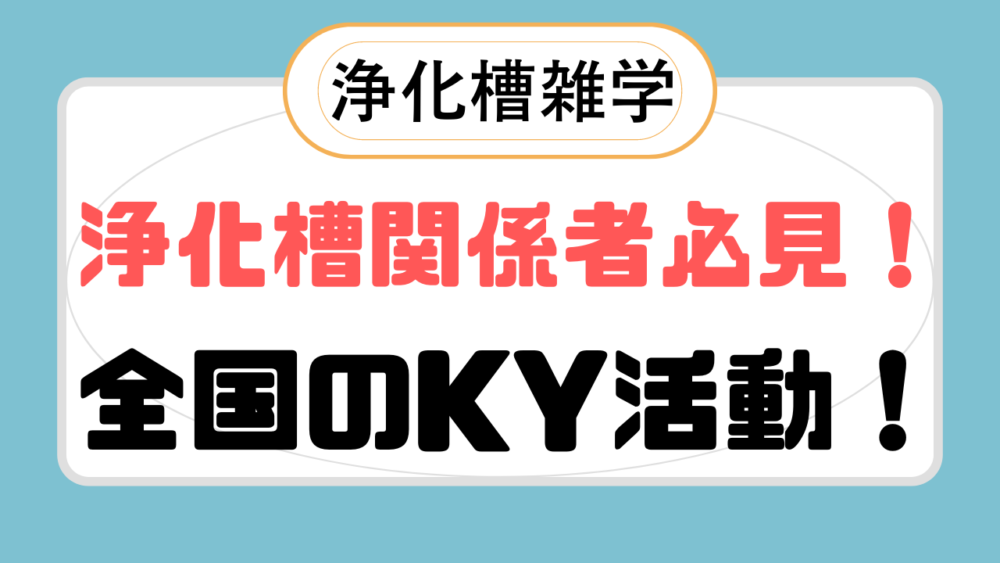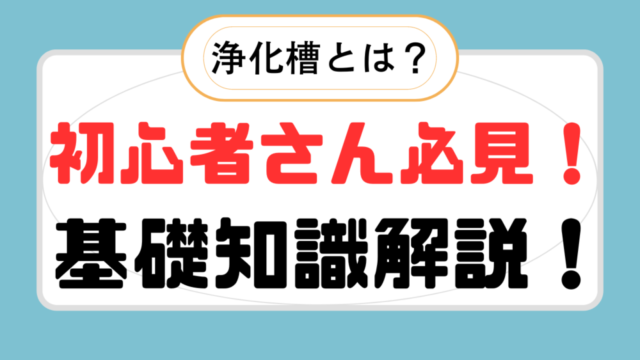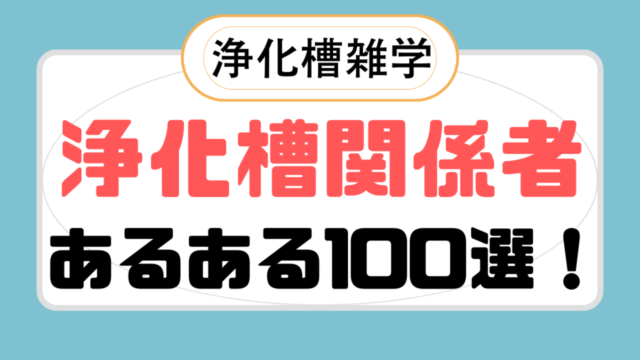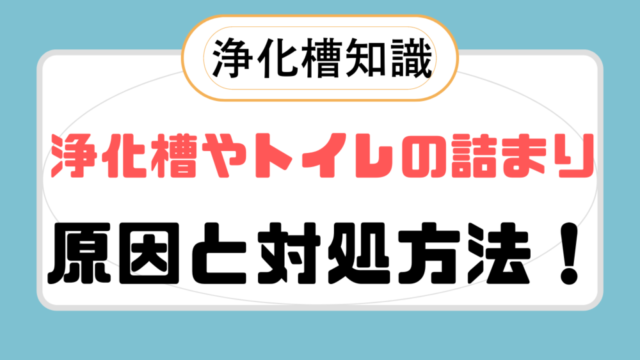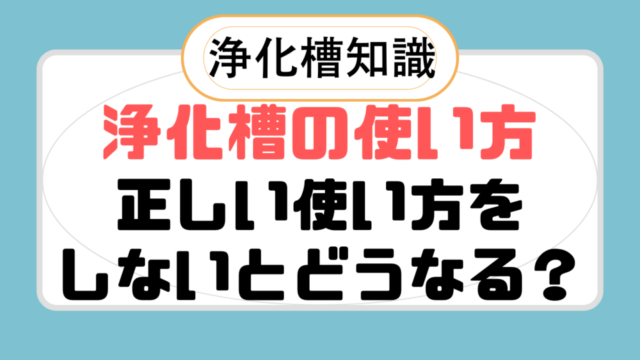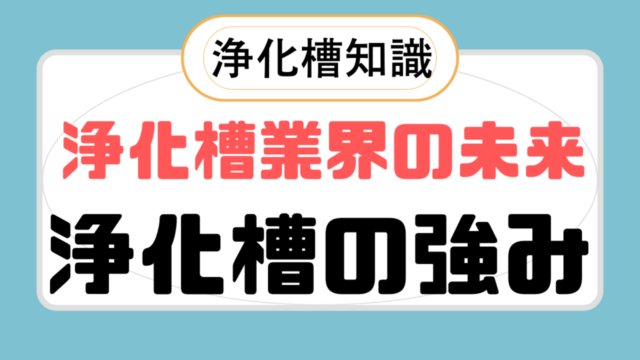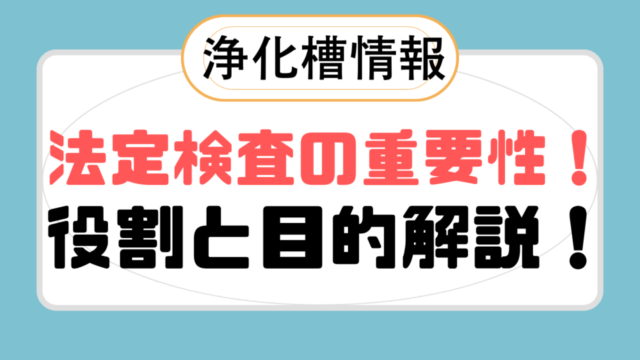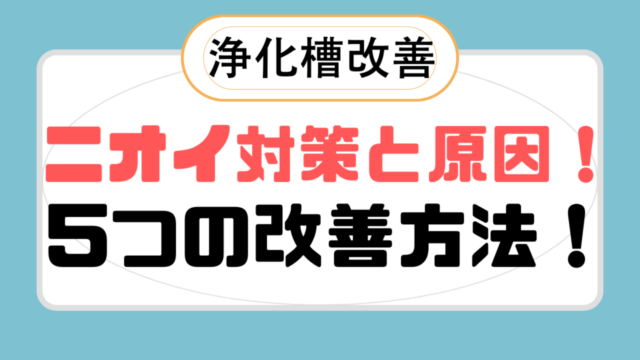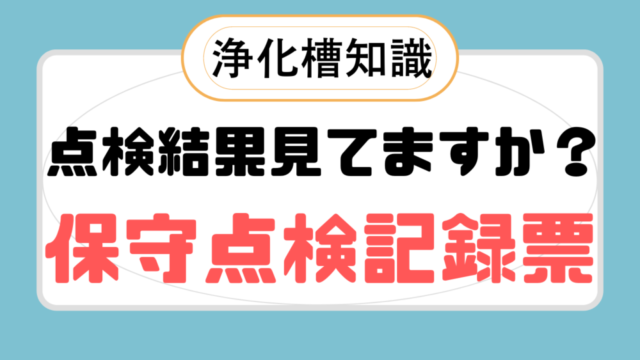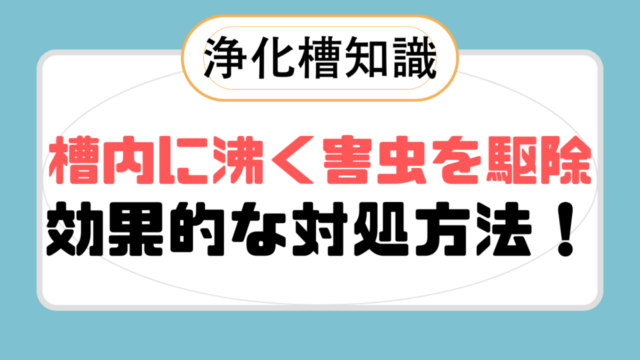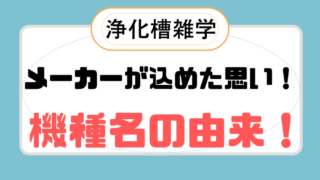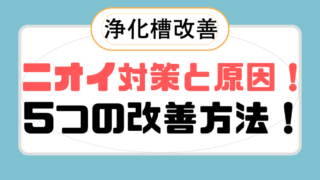今回のテーマ
- KY活動: 他者の取り組みを学ぶ活動
- 一人では気づかない点を発見可能
- 他者の行動や習慣に興味を持つ
本記事では、「全国の浄化槽管理士が取り組んでいるKY活動」について詳しくまとめています。
KY活動は一人だけでなく、組織全体での見直しと実行が重要です。
目的は事故発生のリスクを減らすことです。
記事を最後まで読むと、新たな考え方やアイデアが浮かぶかもしれません。
明日からの業務に取り入れてみる価値があります。ぜひお読みいただき、浄化槽管理に役立ててください。
Contents
KY活動とは危険予知活動

危険予知活動(KY活動)は、通勤、勤務中、退社途中など、日常のあらゆる場面で無意識に行われています。
危険予知は常に「考える習慣」を持つことが非常に効果的です。運転においても、可能性のある危険や予測される事態に対して意識的に対策を取ることが重要です。
事故を回避するために危険予知を実践した経験を持つ方も多いのではないでしょうか?
危険予知の限界を超える方法とは?チームで取り組むKY活動
危険予知の習慣化について考えてみましょう。
もし10個以上の具体的な危険予知が思い浮かぶ方は、既に危険予知の習慣を身につけていると言えます。
しかし、ほとんどの方は10個以上を思いつくことは難しいでしょう。
そこで、今後の参考になるようにKY活動(危険予知活動)を紹介します。この活動を通じて、日常の様々な場面で危険を予測し、事故を未然に防ぐことが目指されています。
安全な車両移動を実現するKY活動のポイント
- 歯止めやコーンを設置する
- 狭くて見通しの悪い道は避ける
- 敷地内では最低速度で運転する
- 交差点での進入時は歩行者を確認する
- マンホールや散水栓の上には載せない
- 通学路は避け、走行する際は徐行する
- 学校の休みや連休は特に警戒する
- バックモニターだけでなく、目視で周囲を確認する
- 2人乗車時は相手に声を掛けて確認する
- 余裕を持った運転を心掛ける
- 高低差の場所で停車時、サイドブレーキの確実な使用を確認する
- 子供や高齢者が多く集まる場所では特に注意を払う
- 夜間や悪天候時は、照明やヘッドライトを適切に使用し、視認性を確保する
- 運転席からの視界が遮られる物(マスクや帽子のひさし等)は取り払う
- 正確なミラーの角度調整を定期的に行い、死角を最小限にする
- 運転中は不要な物や操作(スマホ操作など)を避け、集中する
- 長時間の運転後は、適度に休憩を取り、疲れを感じたら無理せず運転を中断する
- 車両に適した速度制限を守る
- 定期的に車両の点検やメンテナンスを行い、安全装置やブレーキの機能を確保する
- 信号機のない交差点や歩行者横断部では、速度を落として慎重に進行する
- 車線変更前や交差点進入前には、十分に周囲を確認する
安全な保守点検と作業のためのKY活動のポイント
- 防虫剤による頭痛の予防
- 消毒剤の吸引によるくしゃみを避ける
- 塩素剤がしっかり溶けているか確認する
- ヘルメットや手袋の着用
- こまめな水分補給を心がける
- ハチやマムシに注意
- 花壇や蛇口を破損させない
- 雑草による導線の不明確な場所の認識
- 子供や動物の気配がある場合は蓋を確実に閉める
- 電動工具使用時の安全確保
- ブロワーやポンプの漏電リスクの管理
- ベルト駆動のブロワーは電源を落としてからの点検
- マンホールの蓋をしっかりと閉じ、安全確認をする
- 槽内への踏み外しを防ぐ
- 出窓や突起物に注意し、衝突を避ける
- 鉄蓋やコンクリート蓋を持つ際の体の負担を軽減する
- 点検終了時の指差し呼称で確認する
清掃作業中の危険予知活動のポイント
- 担体の誤吸引を防止
- 排出、吸引の操作ミスを避ける
- ホースが詰まることを防止
- サクションホースが暴れることによる建築物へのダメージを防ぐ
- スカムを先に吸引し、ろ材の落下や目詰まりを防ぐ
- 浄化槽内の破損をチェック
- 配管やバルブの破損を確認
- 仕切りが割れないように汲む量を適切に調整
- マスクを正しく着用し、汚泥の飛沫から身を守る
LINEオープンチャットへの参加ご案内

多くの管理士の方々が参加するLINEオープンチャットを運営しております。
浄化槽管理士を目指す方や、資格取得を検討されている方は、ぜひこのチャットにご参加ください。
現在、100名以上の経験豊富な浄化槽関係者が参加しており、日々有益な情報交換が活発に行われています。
日本最大の浄化槽コミュニティ!