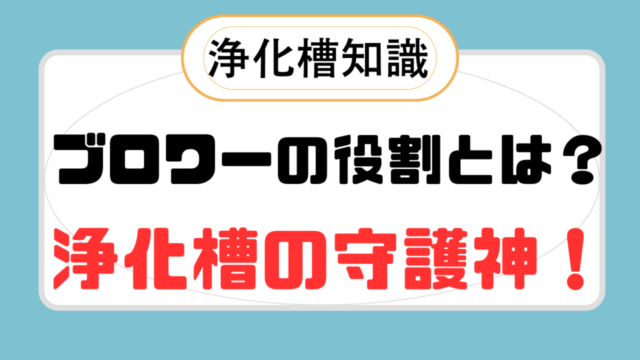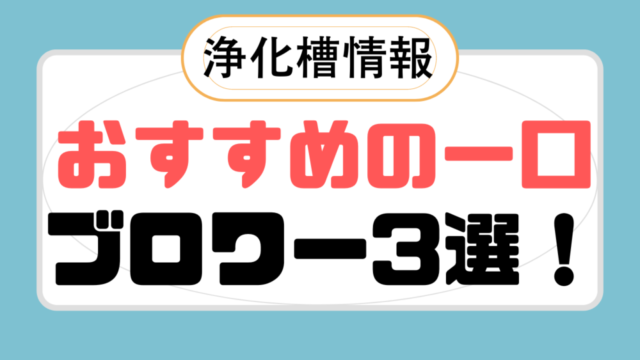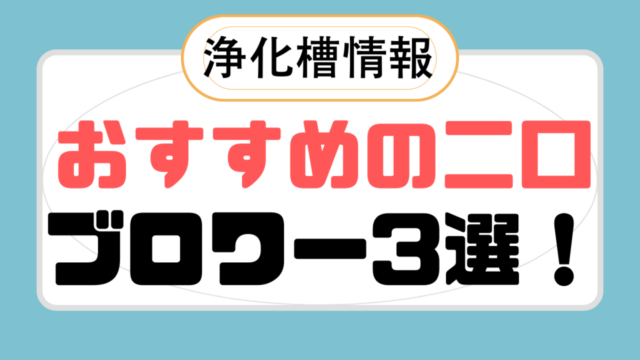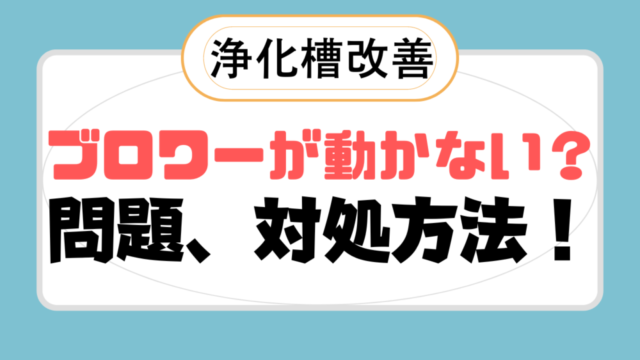ブロワーの故障に悩まされたことはありませんか?実は、ブロワーが故障する主な原因として、圧力の低下や過負荷が隠れていることがあります。
ブロワーにはそれぞれ「定格圧力範囲」という、運用すべき適正な圧力範囲が設定されており、この範囲を超えると故障のリスクが高まります。
このような不測の故障を防ぐためにも圧力を定期的にチェックすることは非常に重要です。
圧力計の正しい使用方法については動画で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
PDPG-30A圧力計の特長と使い方

- ブロワー本体の適正な圧力を正確に測定可能
- 空気漏れや高負荷の原因を早期に特定・解決
- ダイヤフラムの交換時期やメンテナンスのタイミングが明確になる
PDPG-30Aという「ポータブルデジタル圧力計」です。
この商品は「ブロワーの圧力を測定」することができます。
浄化槽の中で微生物による処理が行われるため、適切な空気供給は極めて重要です。
圧力の低下は微生物の活動を阻害するだけでなく、配管の詰まりやブロワーの故障の原因ともなり得ます。
特に、ブロワーの「ダイヤフラムやピストンは高負荷状態だと故障リスク」が高まります。
この商品を利用すれば定期的に圧力を簡単にチェックでき、潜在的な問題を早期に発見することができます。
ブロワーに異音や風量の低下が感じられる場合に使用をおすすめします。
簡単操作!デジタル圧力計の測定方法

デジタル圧力計の使用は非常にシンプルです。
ブロワーの吐出口に取り付け電源をオンにするだけで、瞬時に圧力を測定することが可能です。
測定の際の具体的な様子は写真で確認できます。
操作の詳細や実際の使用例を動画で見たい方は、以下のリンクをクリックしてください。
ブロワー本体には「常用圧力」と「定格圧力(kPa)」が明記されています。これを基準にして圧力を測定します。
今回の測定では常用圧力が15kPaであり、測定結果が12.9kPaだったため、圧量が低下している可能性が考えられます。
浄化槽の状態によって水位や配管の詰まり具合が変化するため、定期的な測定をおすすめします。
また、前回の測定結果と比較してどれほど変化したかを「目安」として把握することも大切です。
ダイヤフラムは一年で劣化する!

多くの現場で測定を行った結果、ブロワーは「一年以上使用すると常用圧力が必ず下がる」ことが明らかになりました。
製造メーカーは、内部のダイヤフラムという部品を年に一度交換することを推奨しています。
ただ、お客様の費用の都合や手間を考慮すると、交換が行われないことが多いことが現状。
部品交換を怠った多くの現場では、圧力計による測定で常用圧力の低下が確認されました。そして部品を交換した後、圧力が適正な範囲に戻ることも確認できました。
これにより、「メーカーが一年で部品交換をおすすめする理由」が理解できました。
空気量の不足は微生物への影響だけでなく配管の詰まりの原因にもなります。
この問題は、圧力計の測定を行わないと気づくことが難しいものです。
浄化槽の正常な運転を維持するためには、ブロワーの内部部品の定期的な交換が必要です。
検証動画で明かされる驚きの結果!
ぜひ以下の動画をご覧いただきブロワーの新規交換の様子を確認してください。
動画を通じてよりわかりやすく理解していただけます。
浄化槽満水状態から正常な水位に戻るまでの圧力測定動画はこちら↓
ブロワーダイヤフラム交換時の圧力測定動画はこちら↓
おわりに

こちらのアイテムは持っていると非常に便利です。
浄化槽でのトラブルは予測が難しいものですが、アイテムを利用することで問題の原因を迅速に特定することができます。